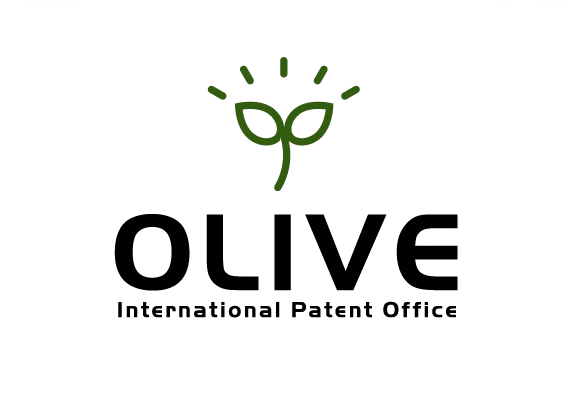NEWS
新着情報
<弁理士コラム>ChatGPTと特許業務の未来(第2回)

前回のコラムでは、ChatGPTが特許業務に与える影響について述べました。AIの活用により、技術情報の収集や文章作成が飛躍的に効率化される一方で、AIが人間の意図を完全に汲み取ることは難しいという課題も指摘しました。今回は、さらに踏み込んで、AIが今後どのように特許業務に関与し、どのような進化を遂げる可能性があるのかを考察したいと思います。
AIは弁理士の補助者になり得るか?
現在、ChatGPTは、技術的な背景調査を補助したりするツールとして利用されています。しかし、弁理士の判断を完全に代替するには至っていません。では、AIは今後どこまで活用できるようになるのでしょうか。
1.クレーム(請求の範囲)作成の自動化の可能性
AIは、技術文献や過去の特許を分析し、最適なクレーム構成を提案することが可能になりつつあります。しかし、クレームの記載は発明の保護範囲を決定する重要な要素であり、慎重な検討が求められます。
2.特許調査の効率向上
既存の特許検索ツールに対して、AIを補助的に利用することで、効率の良い検索が可能になってきています。類似技術の自動抽出や、関連する判例の提示も可能になるかもしれません。
3.審査対応の補助
AIが特許庁の拒絶理由を解析し、過去の審査事例を基に最適な意見書のドラフトを作成する機能も今後期待されます。
AIが苦手な領域
技術の進歩が進むとはいえ、AIにはまだ苦手な領域があります。
・法律的な判断や戦略的なアプローチ
AIは過去のデータを基に各種情報を提供しますが、新規性・進歩性の解釈やクレーム戦略の決定には、専門家の経験や勘が重要になります。
・依頼人とのコミュニケーション
AIは技術情報を整理できますが、依頼人の意図やビジネス戦略を理解し、適切なアドバイスを提供するにはまだ限界があります。
今後の展望
AIが特許業務において「補助的な役割」から「実質的な判断を支援する役割」へと進化するのは時間の問題かもしれません。しかし、現時点ではAIはあくまで弁理士の補助ツールであり、最終的な判断は人間が行う必要があります。
AIが進化し続ける中、弁理士としての役割も変わっていくことでしょう。ルーチン業務の効率化が進む一方で、創造的な仕事や戦略的な判断に時間を割くことが求められるようになるのではないでしょうか。
ここで、別の角度からの視点をいくつか提供したいと思います。
1.「AIが発明者になった場合、特許は取得できるのか?」
実際にAIが発明者と認められないと判断された裁判例もあり、今後、法改正が必要かどうかが検討されています。
2.「AIを活用しすぎると、発明の価値が下がる?」
誰でもAIを使って発明できるようになれば、大量の発明により、相対的に各発明の価値が低下する可能性があります。逆に、弁理士の「創造的な貢献」がより重視される時代になるかもしれません。
3.「特許庁の審査官もAI化する可能性」
AIが出願書類を審査し、発明の新規性や進歩性を判断する時代が来るのでしょうか。AI審査官が導入された場合、人間の審査官はどのような役割を果たすべきでしょうか。
4.「AIが作成した明細書は、誰が責任を持つのか?」
弁理士に頼らず、出願人自らがAIの生成した文章で出願をした場合、その責任は出願人にあるはずですが、AI開発者に責任を負わせる出願人が出てきかねません。
AIの活用には、単なる効率化だけでなく、特許制度や弁理士の役割自体に影響を与える可能性を秘めています。今後、AIがどのように進化し、特許業務にどのような影響を及ぼしていくのか、引き続き注目していきたいと思います。
弁理士 三苫貴織